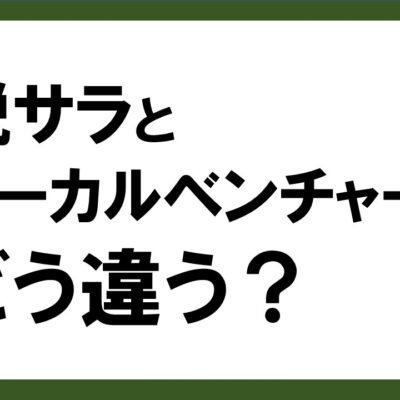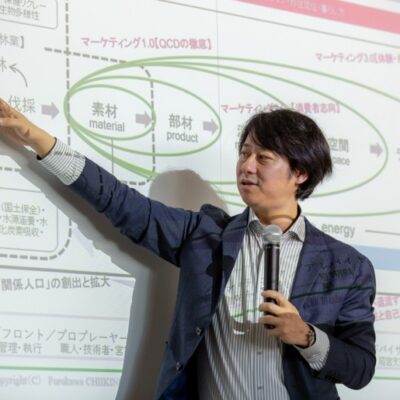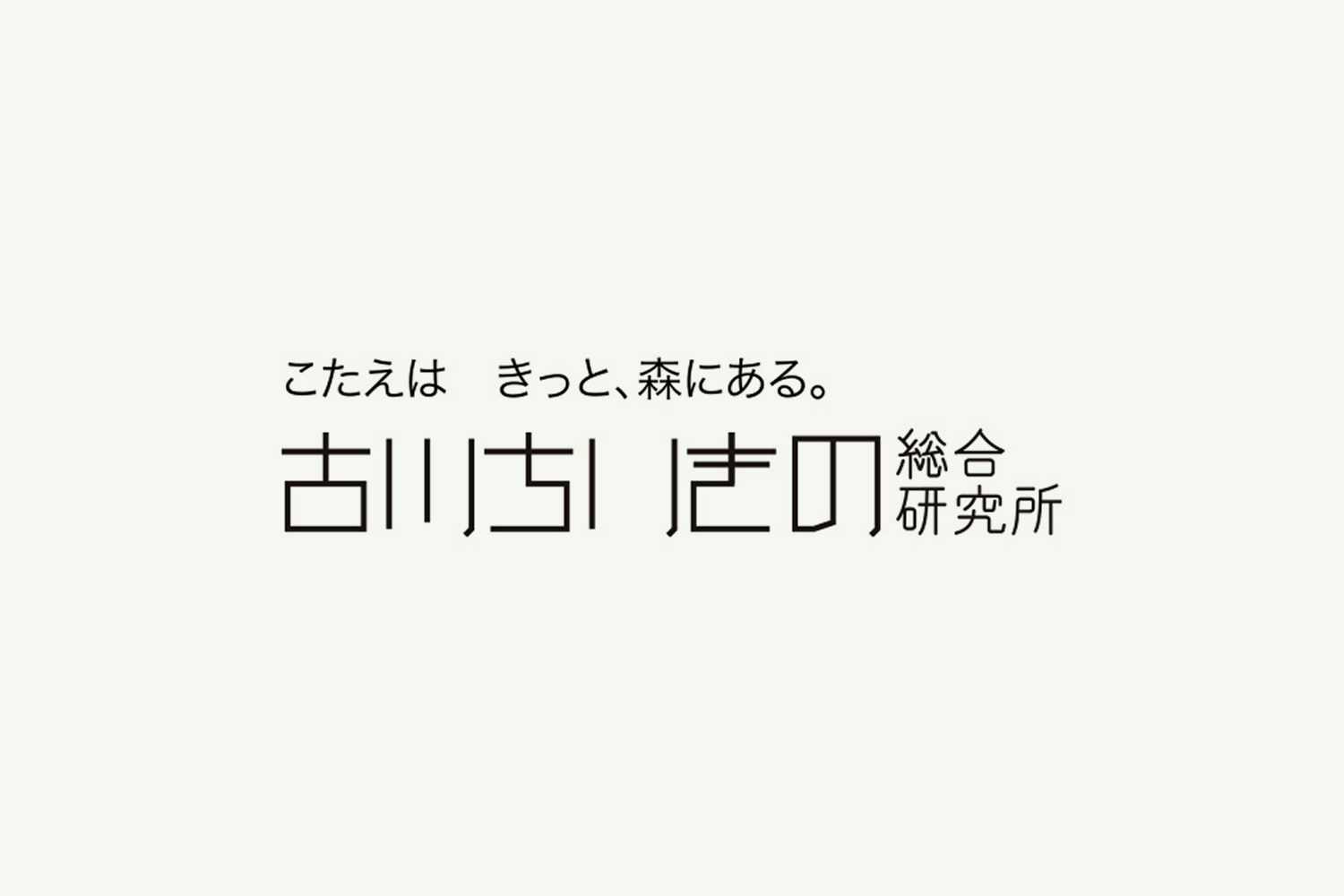2024年度インターン生の富岡です。
2024年5月21日から23日に同行させて頂いた出張に関して、奮闘記録を2回に分けて紹介しておりこの記事は後編となります。
前編はこちらからご覧ください(https://chiikino.jp/blog/?p=11506)
後編では高知県本山町への出張で見て触れて感じて学んだことを紹介します。
5月22日(水)、徳島県三好市から高知県本山町へ向かっている最中も古川さんから学ぶことはたくさんありました。
「間伐には林道が必要。」「SMARTの法則で目標設定をする。」
移動中も自分の頭になかった新しい情報がどんどん入り、メモをたくさんとりました。
メモに追われながら車で1時間。高知県本山町役場に到着すると、目の前には木の外壁で彩られた建物がありました。その建物は築2年の新しい本山町役場で、その造形に魅了されるとともに主役として木材を使用するだけでなく”魅せるもの”という付加価値として活用する方法もあると気付かされました。そして役場近くにある沈下橋を横目に、本日の現場に向かいました。


業務と勉強の両立で頭がパンクした話
三好市に引き続き2日目の打ち合わせでも議事録の作成をお願いされました。そしてこの日の夜も、懇親会があり、人生2回目のスナックも経験しました。
まさかこの出張で人生2回目を2回分体験すると思ってもいませんでしたが。前日の反省をふまえ飲み過ぎないように十分注意し、次の日に備えました。
(以下写真は、懇親会での赤牛ステーキ。とても美味しかった。)

5月23日(木)、本山町地域おこし協力隊に向けた研修に同行しました。
こちらの業務でも議事録の作成をお手伝いさせて頂きましたが。これまでの業務と異なり”研修”の議事録であるという点で違いがありました。
三好市の時には自分の知らない言葉が出てくると、その意味を調べて議事録に書き込むという作業でしたが、
本山町の時には知らない言葉が出てくるとともに、移動中の車内で勉強したSMARTの法則のようなフレームワークがたくさん出てきたため、自分の中で噛み砕いてメモをしながら、議事録に書き込むという、1日目からさらに1段階上の作業を行ないました。
作業量の多さから、三好市と同じ方式だと追いつかないと感じ、自分の中でルール設定をして臨みました。
①古川さんの話したことを議事録に書く
②議事録の中から自分の参考になる情報をメモ帳に抜き出す
③少しの休憩時間でメモから自分ごと化する
という3つのステップを踏むことで、勉強会に関する議事録をまとめなければならないという”やるべきこと”と、勉強会の内容を頭に入れたいという”やりたいこと”の両立を行い、ルール化して要点をまとめて簡潔に書くことに挑戦できたとともに、いかに短い時間で勉強したフレームワークをメモして”自分ごと化”するかという方法も身につけることができました。この二つは今でも大いに役立っており、現在でも支援業務の際には毎回行っています。

日本一の大杉
車で帰っている途中に
「そのまま帰るのはもったいないので、せっかくなら大杉を見に行こう」
と古川さんから提案いただき、大豊町にある”杉の大杉”を訪問しました。
そこでは、子どものポスター、大杉の魅力、歌碑の3つに学びを感じました。
初めに、”子どものポスター”ですが、先に以下の2枚の写真を見てください。


このようなポスターが大杉の入場口の近くに5枚ほど貼っていました。
このポスターを見た時に、”子どもの影響力は多くの人の心を動かすことができる”ということを感じました。このポスターは「大杉を支援するためにも無断で入らずに入館料を払ってください」というメッセージが込められたポスターなのですが、これを見て「無断で入ろう」という人は出ないのではないかと思いました。
大人が言うよりも何倍も効果のあるものだと感じ、子どもが発信してくれることへの効果の可能性を感じました。その気づきを活かして、子どもたちが木材や林業のことを発信していくことで、さらに木材の可能性を広げていくことができるのではという考えを持つことができました。
2つ目は’’大杉の魅力”に関してです。
杉の大杉は、大豊町にあり杉の木2株が合体したもので樹齢3000年以上とも言われており、樹高が60mを超える非常に迫力のある杉の木でした。
大杉を見た時に、”偉大さと寂しさ”を感じました。
3000年という自分たちが見たことのない歴史をこの木は見ており、その中で生き残っている逞しさから尊敬の念を覚えたことはもちろんですが、それに加えて大杉自体が機械のように鉄板で保護されていることから”木として生きる“ということに違和感があり、これがこの木にとっての自分らしさなのかと考えてしまう部分もありました。毎度、業務の後には古川さんから「物事の良い点と課題点をあげてください」と言われていたため、そのような多方面から物事を見る癖がこの時からついていたように思います。

最後に”歌碑“に関してですがが、大杉から少し進むと大豊町や本山町を流れる吉野川と歌碑を一気に見ることができるスポットがある。その石碑は歌手である美空ひばりさんの”川の流れのように”の歌詞が書いてある歌碑でした。
かつて、美空ひばりさんが大杉に「日本一の歌手になれるように…」と願掛けを行ったことから、美空ひばりさんが亡くなって以降、大杉近くに建てられたものとのことです。
その歌碑の近くにはボタンがあり、そのボタンを指差しながら「このボタンを押してみて」と古川さんが言ったので押してみると美空ひばりさんの名曲である”川の流れのように”が流れ始め、吉野川を見つめながら、古川さん、高田さん、私の三人で曲に浸りました。
曲を聴きながら、ふと感じたことがあった。それは様々な年代の人が3人いて、全員が知っていて歌えるという曲の”影響力”です。世代が異なる3人の心を動かせるような曲のエネルギーを感じたとともに、大杉があることでこれほどに影響力のある曲を生み出すことができたと思うと、人と自然との関係は切っても切れない関係なのだと改めて感じることができました。

終わりに
3日間あった出張もこれにて終了。
帰路でもメモを書く場面がたくさんありました。出発当初は車内でメモをとることすら慣れなかったのですが、帰りには車でメモを書くことにも慣れていた気がします
(後から確認すると本出張だけで17ページのメモを残していた…。)
西中島南方駅の近く、峠の到着間近。
メモしている自分を見て、古川さんがふと。
「車の中でメモを書き続けることができるのは特技だと思う」と言っていただきました。
今までレクチャーをしていただいていた古川さんの口から、突然の褒め言葉が出てきて驚きを隠せなかったのですが、「自分にも強みがあったんだ」とすごく嬉しかったことを覚えています。
“突然の一言から始まり、突然の一言で終わる。”
今考えてみると古川さんらしいと感じた出張で、そこにはたくさんの学びがたくさん詰まっていました。
次はどこへいくのだろう。はじめの緊張とはうって変わって、毎回のように新しい知識が入ってくることにワクワクしている自分がいます。
「次はどんな経験/ワクワクを求め、どんな学びを得ようか。」
そんな”勉強好き”のまま、今日もオフィスでインターン生として文章を書いています。